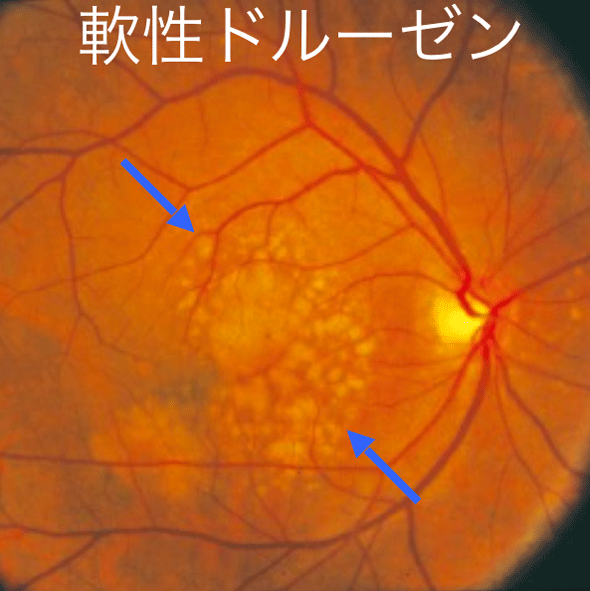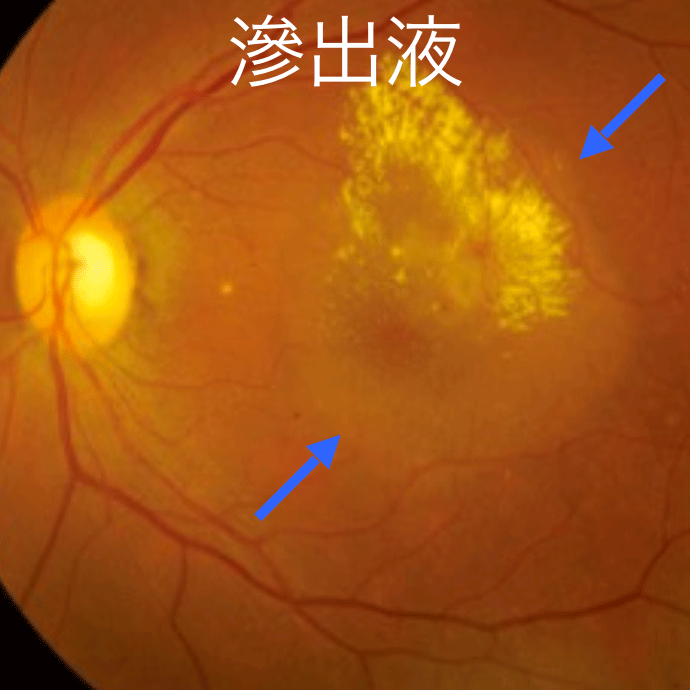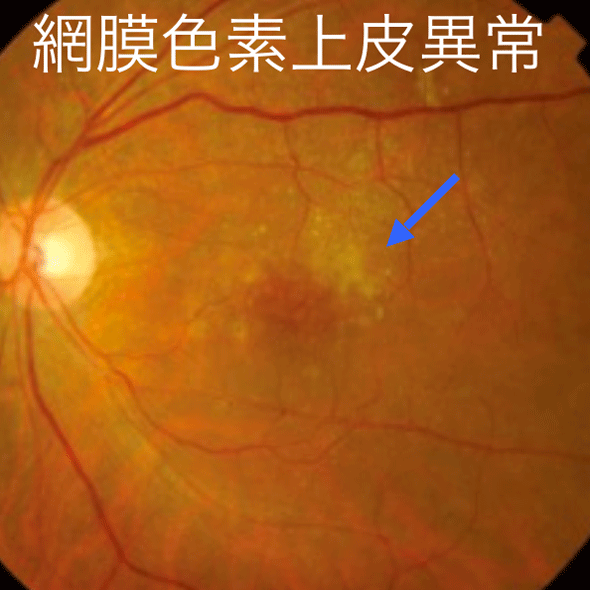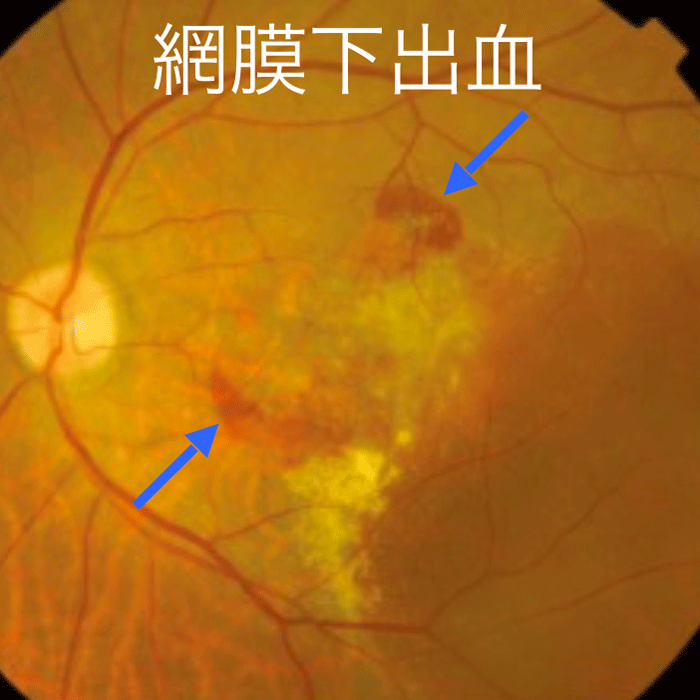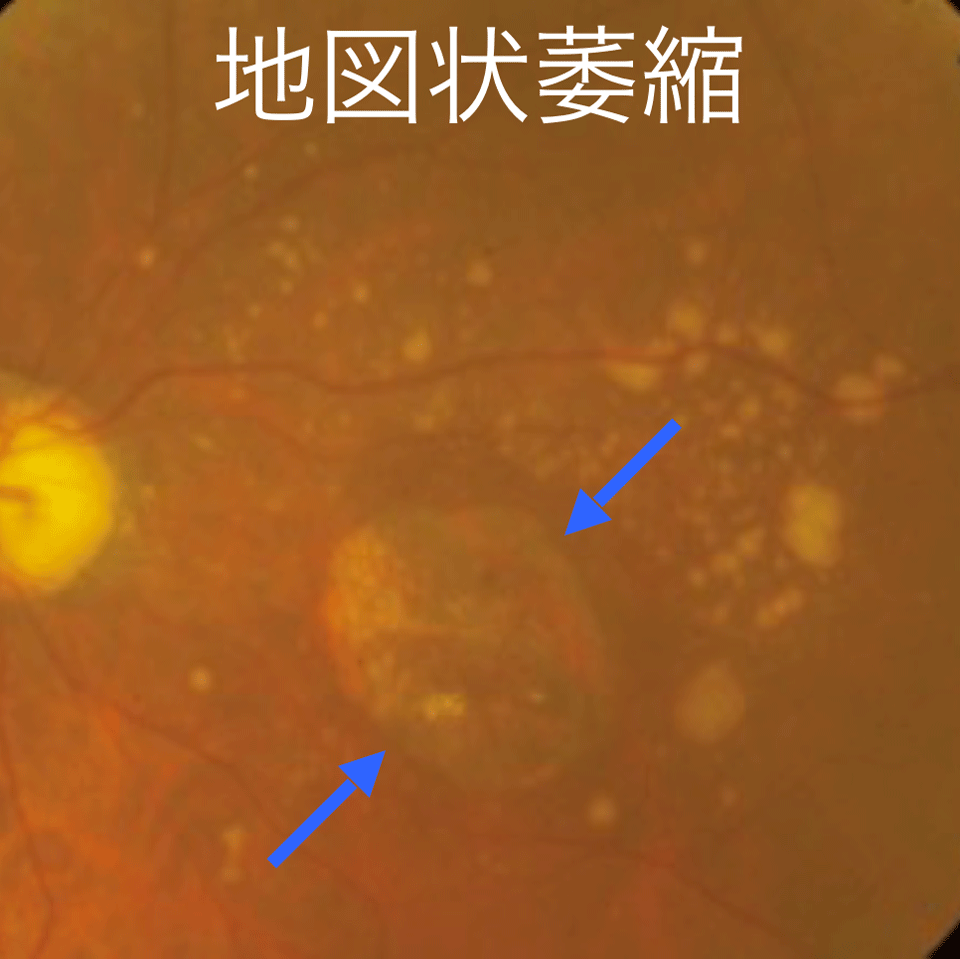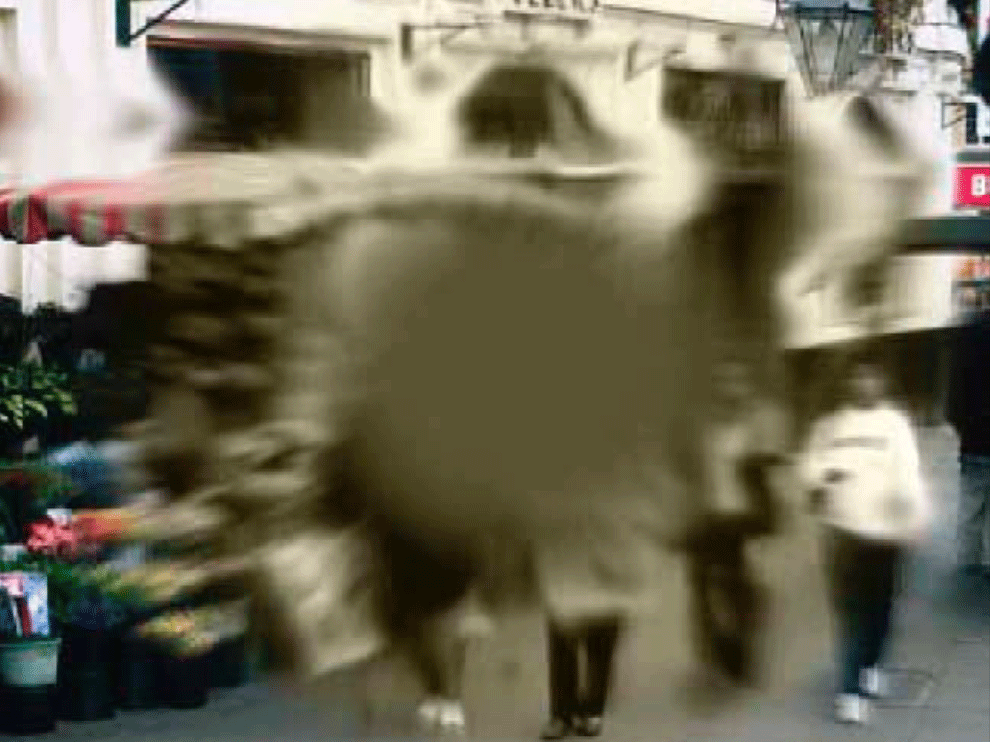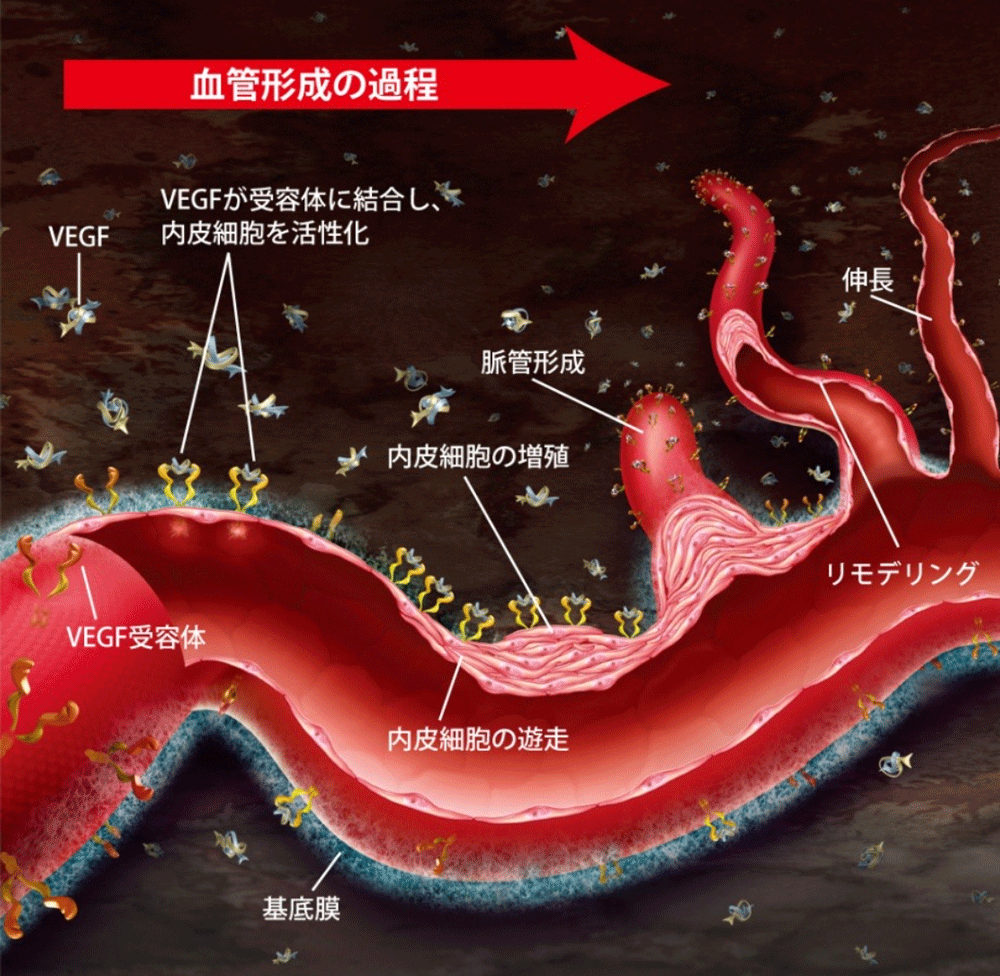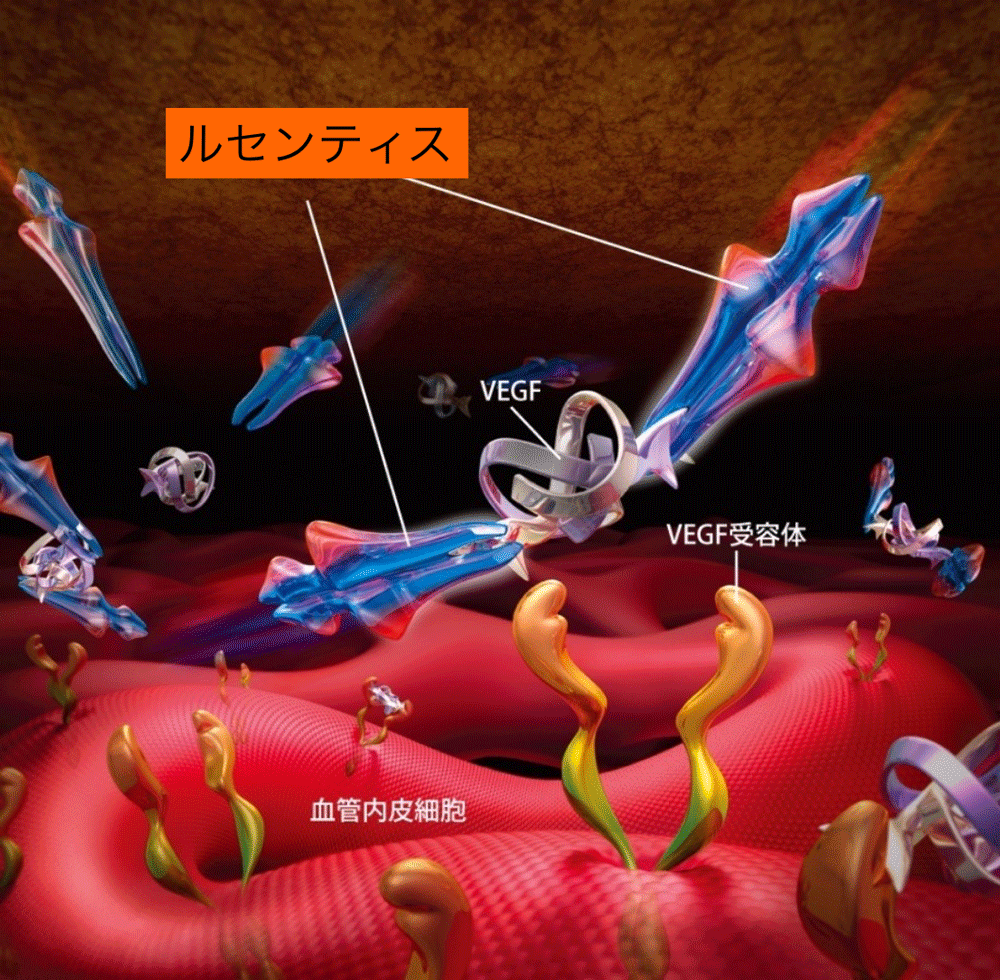疾患別
加齢黄斑変性症治療
網膜の下の脈絡膜から血管が上に伸びてきて、網膜の下や上に出血したり、むくみをおこして視界の中心部が見づらくなる「黄斑」に、異常が生じる眼の病気です。失明につながる病気で、加齢(老化)が主な原因です。症状はゆがんで見える程度から、中心が全く見えなくなる重症のこともあります。
加齢黄斑変性症について
加齢黄斑変性症は増加中
欧米では中途失明の原因のトップがこの病気です。日本ではもともとあまり多くない病気だったのですが、生活習慣の欧米化の影響からか徐々に増え、現在は第4位となっています。
欧米では成人失明原因の第1位
- 米国では約175万人 (2004年の調査結果より)
- 視力が短期間で急激に低下し、失明にいたることも多い
日本でも増加中
- 50歳以上の方の滲出型加齢黄斑変性症の有病率は、1.3%(2007年, 久山町研究)。1998年は0.9%
- 日本での滲出型加齢黄斑変性症の患者さん数は、推定70万人。
- 喫煙が大いに関与している。
- 増加の原因は、人口の高齢化や生活様式(特に食生活)の欧米化と考えられている。
加齢黄斑変性症 2つのタイプ
滲出型(ウエット型)
- 網膜の外側から異常な血管「新生血管」ができ、網膜に浮腫(むくみ)や出血を起こし、急激に視力が低下する。
- 早期から症状がでる
- 失明する人の大半がこのタイプで、日本人に多い。
萎縮型(ドライ型)
- 黄斑が萎縮する
- 進行が遅く、ゆっくり視力が低下する
- 欧米人に多く、日本人に少ない。
加齢黄斑変性症の眼底
前駆症状(前ぶれ)
滲出型加齢黄斑変性症
萎縮型加齢黄斑変性症
滲出型加齢黄斑変性症
滲出型加齢黄斑変性症の黄斑
網膜の重要な部分である黄斑に異常な血管(新生血管)ができる。新生血管はもろく、すぐに壊れて出血を起こす。
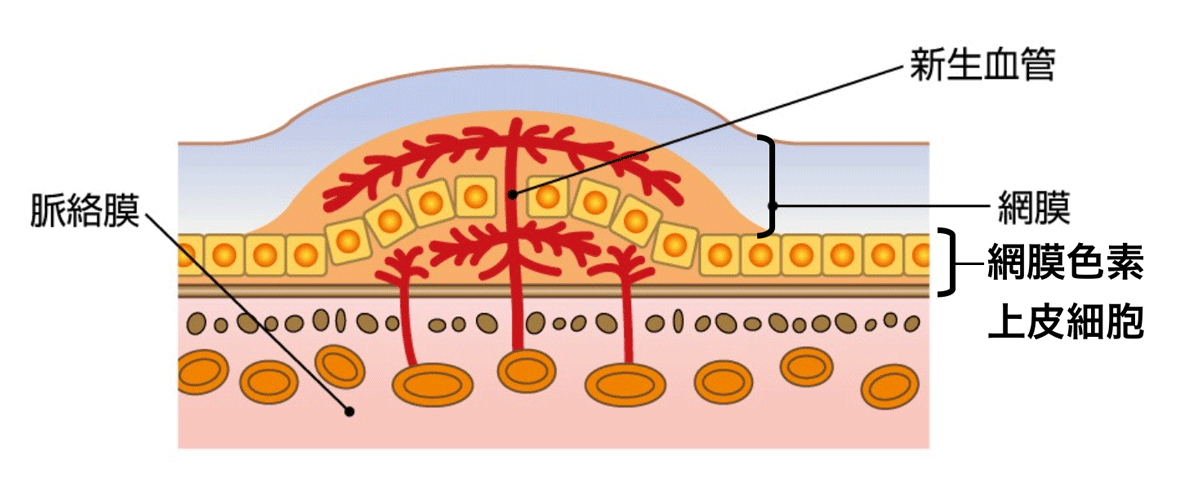
放っておくと、視力が徐々に低下
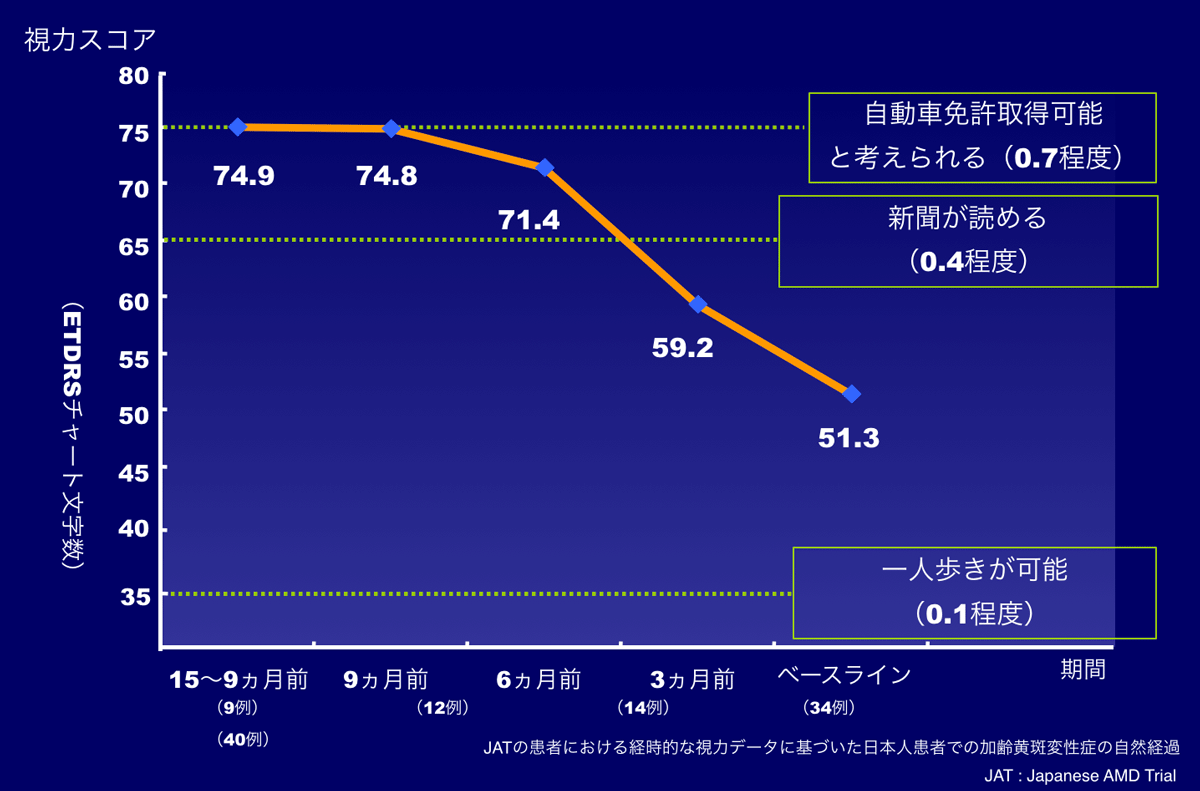
滲出型加齢黄斑変性症の症状
- 部分的、または中心が暗く見える。
- 視界がゆがむ。
- コントラストが低下する。(ものが薄く見える)
- 視力が急激に低下することがある。
症状①
症状②
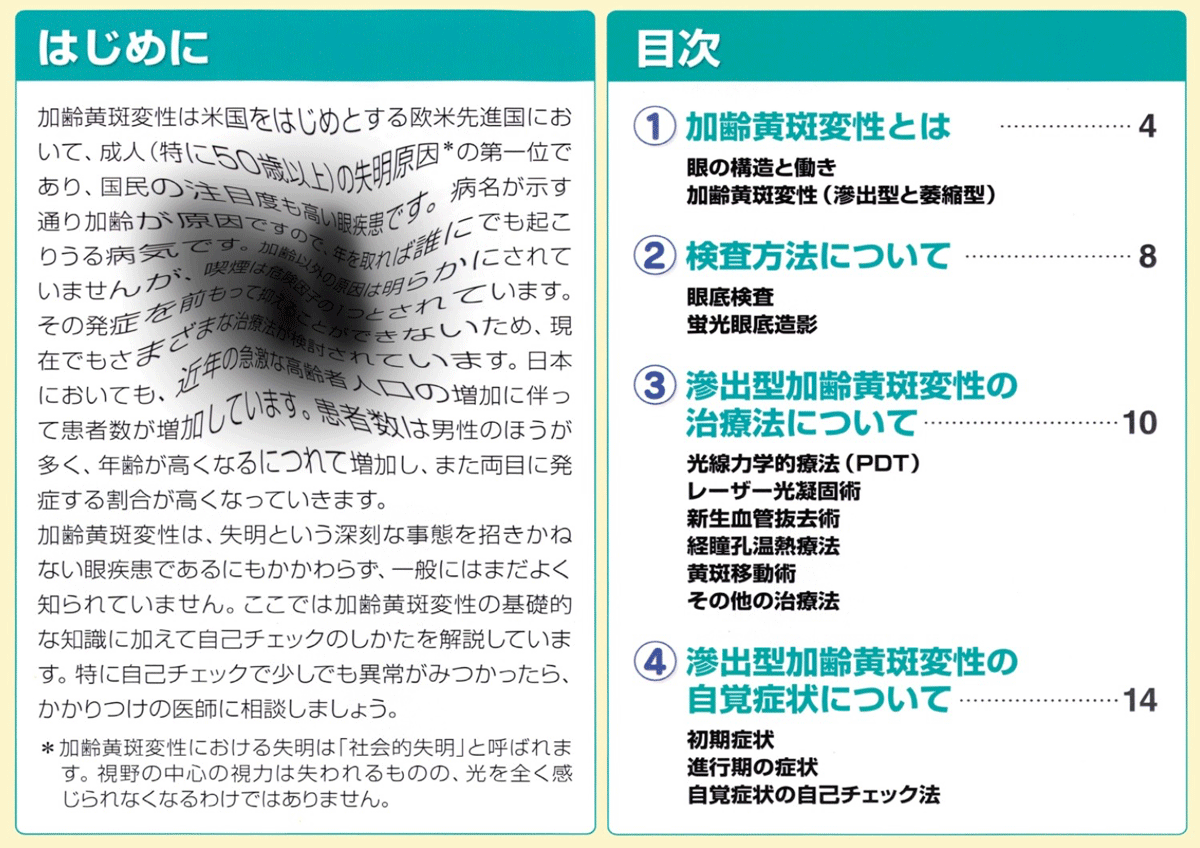
症状③
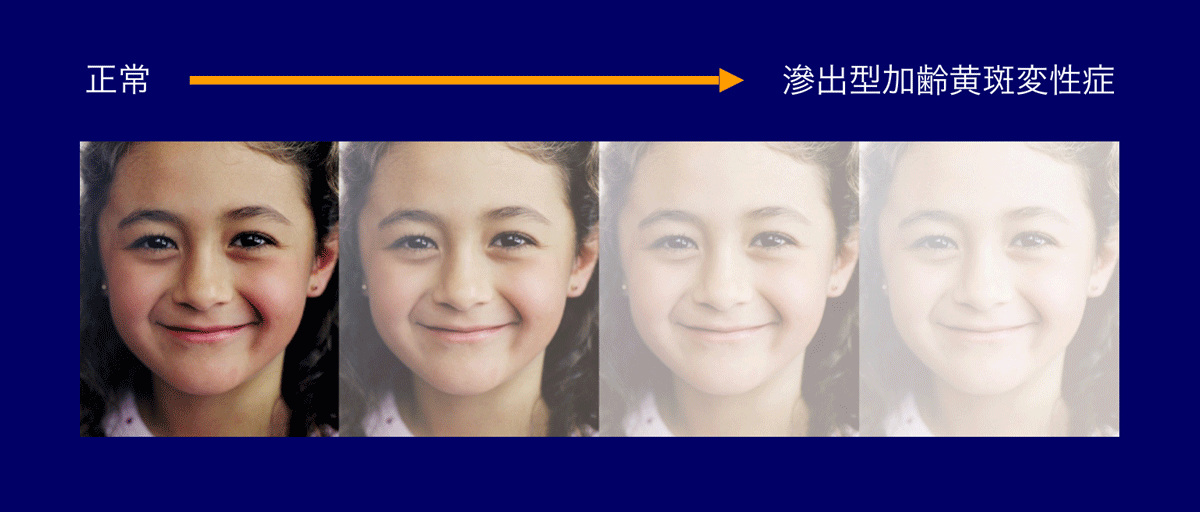
加齢黄斑変性症の原因
環境原因
- 喫煙
- 偏った食生活 (野菜、果物など抗酸化作用のある食物の不足、“悪玉”と呼ばれる脂肪の過剰摂取)
- 紫外線
- 運動不足、肥満
経年的原因
- 年齢
- 白内障手術
遺伝的原因
- 遺伝/家系
- 女性
- 人種(白人)
- 虹彩の色が明るい
加齢黄斑変性症の診断検査
アムスラーチャート
アムスラーチャート自己チェック
- 30cm離れて見る
- 片目ずつチェックする
- 老眼鏡をかけたままチェックする
加齢黄斑変性症の場合の見え方
- 線がぼやけて薄暗く見える
- 中心がゆがんで見える
- 部分的に欠けて見える
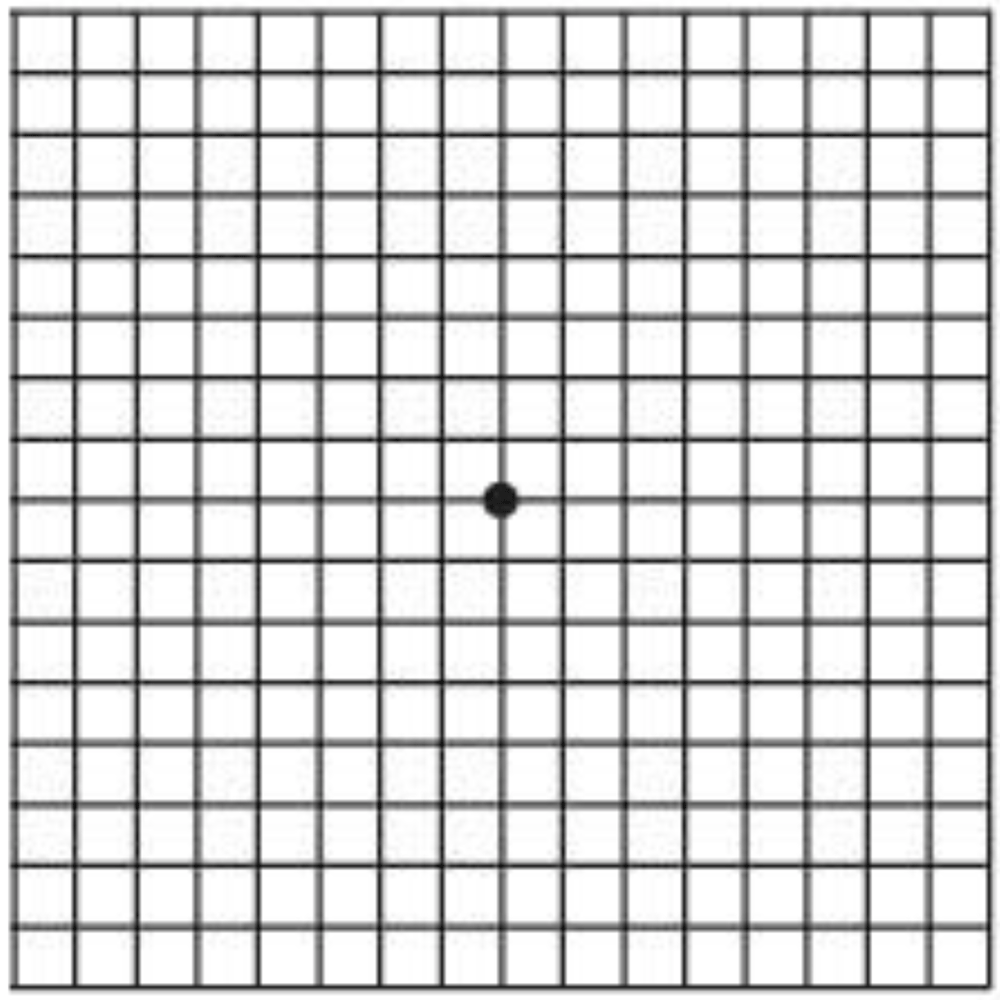
視力測定
-
小数視力検査表 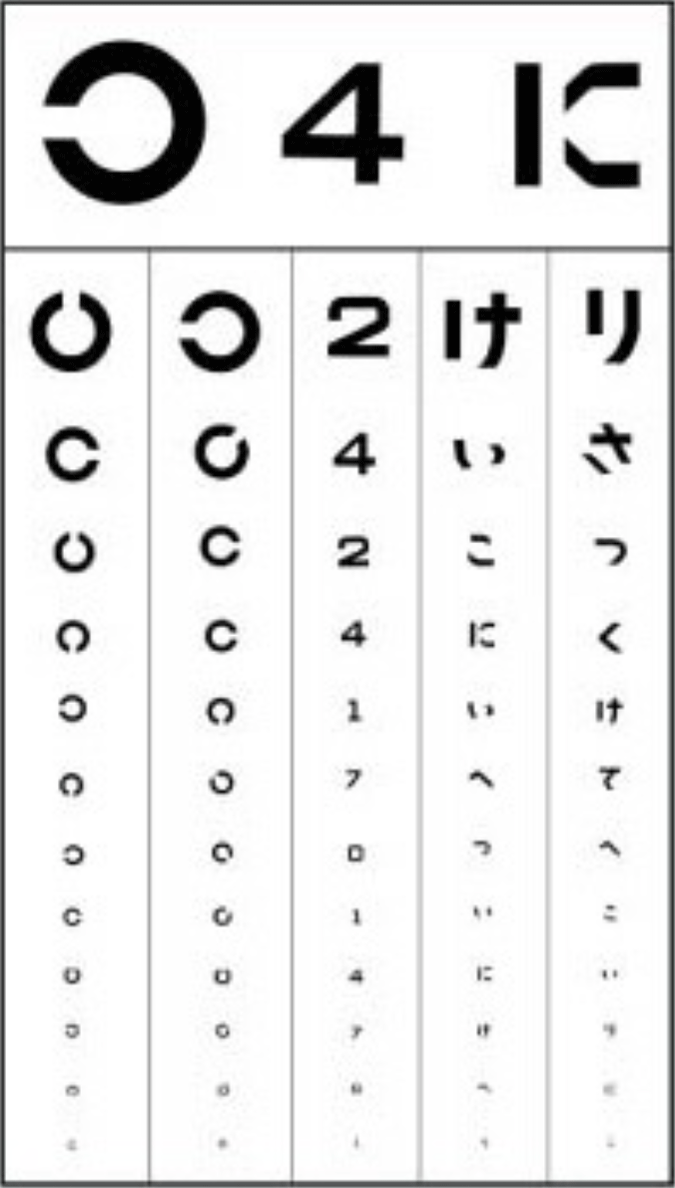
-
ETDRSチャート 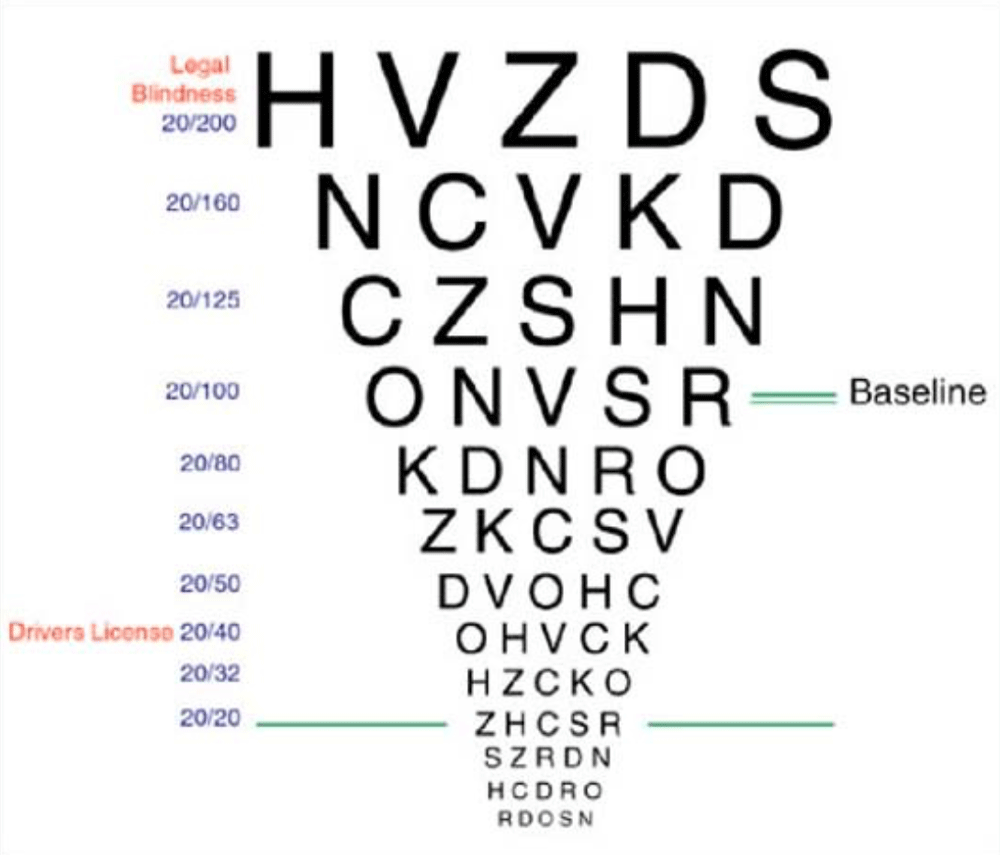
ETDRSチャートでは、視力が低い方のわずかな視力変化が、小数視力検査表よりわかる。
-
ETDRSチャートでの視力変化 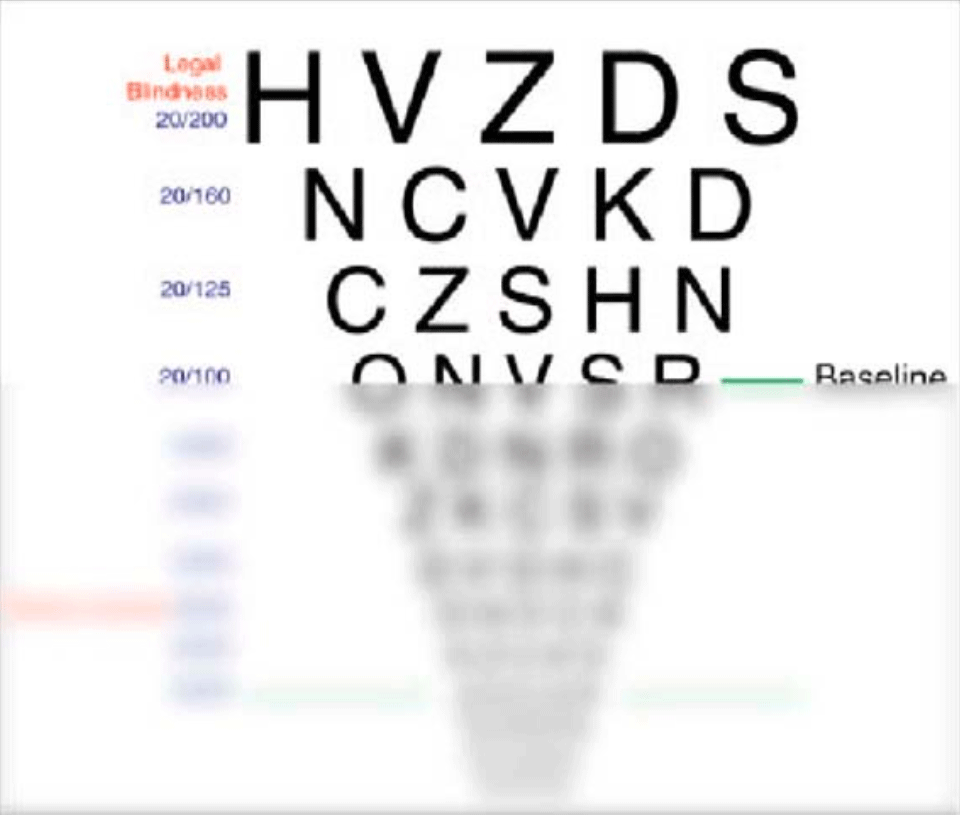
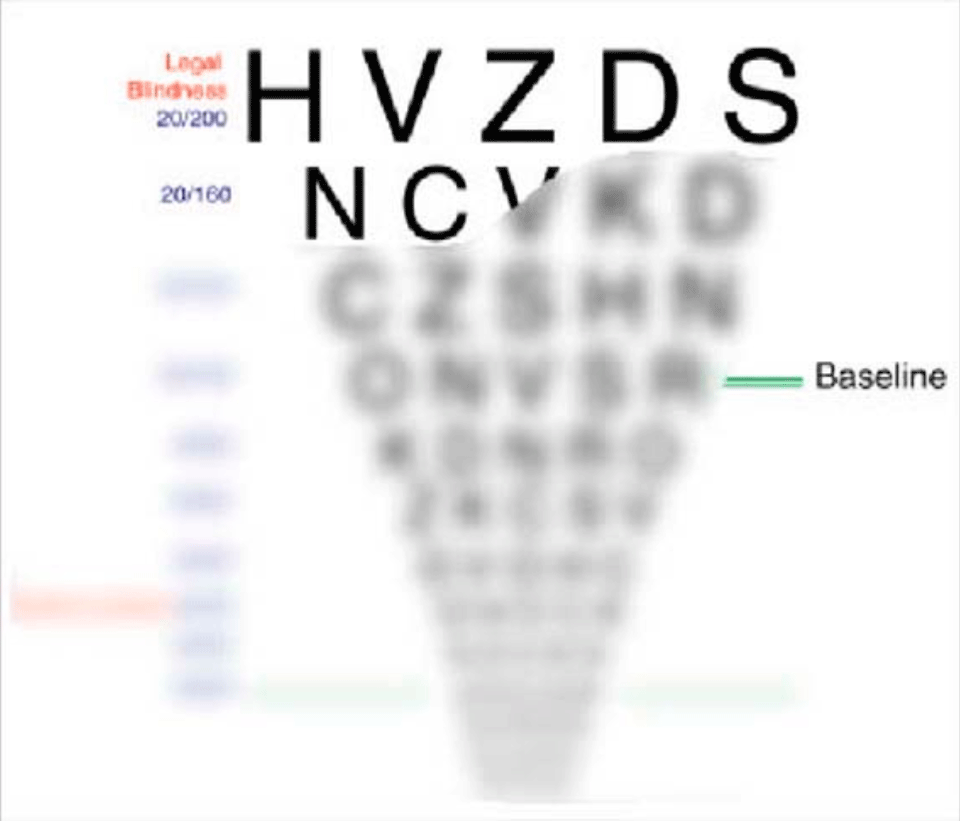
眼底の検査
- 細隙灯顕微鏡
- 光干渉断層計
- 蛍光眼底造影
-
1.細隙灯顕微鏡による検査
眼底に細くて強い光を当て、網膜の病気の部分を拡大して調べます。滲出型加齢黄斑変性症の場合、滲出液、出血、網膜のむくみなどの症状が見つかります。
-
2.眼底写真撮影
眼底カメラにより、眼底のカラー写真を撮影します。散瞳薬を用いる場合と、暗い部屋での自然散瞳を利用する場合があります。
-
3.光干渉断層計(OCT)による検査
網膜の断面の状態を詳しく調べます。滲出型加齢黄斑変性症の場合、網膜剥離(網膜がうき上がる)、網膜のむくみ、新生血管(異常な血管)などが見つかります。
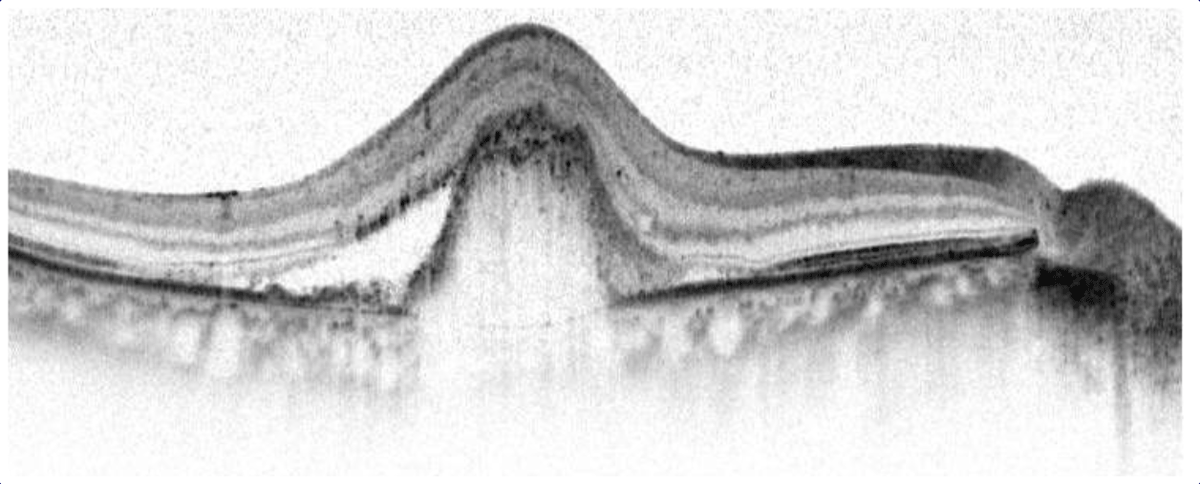
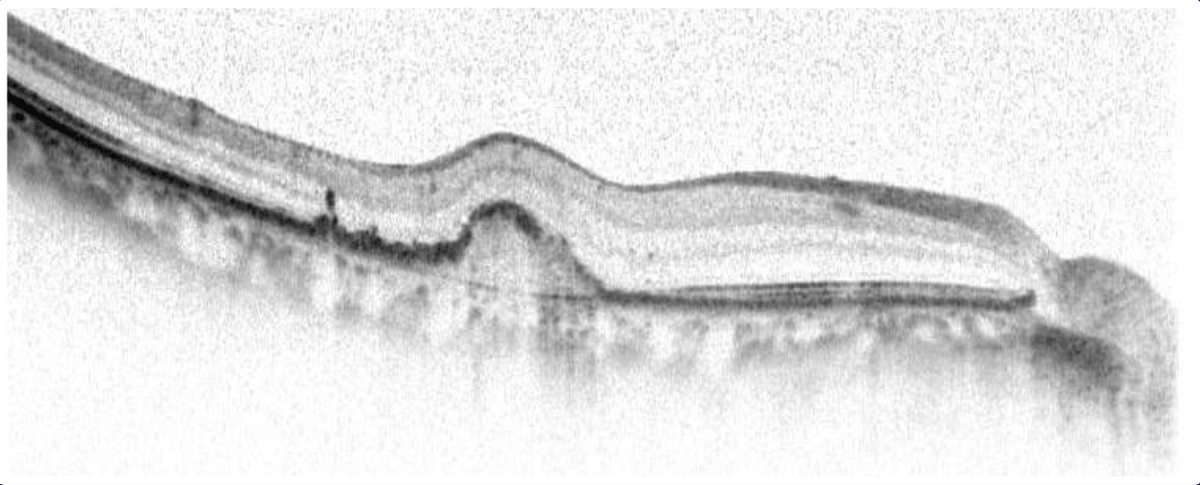
-
4.蛍光眼底造影検査
蛍光色素を含んだ造影剤を腕(静脈)から注射し、眼底カメラで眼底の血管の異常を検査します。新生血管(異常な血管)や、新生血管からもれた血液がどこにあるのかがわかります。
-
フルオレセイン蛍光眼底造影
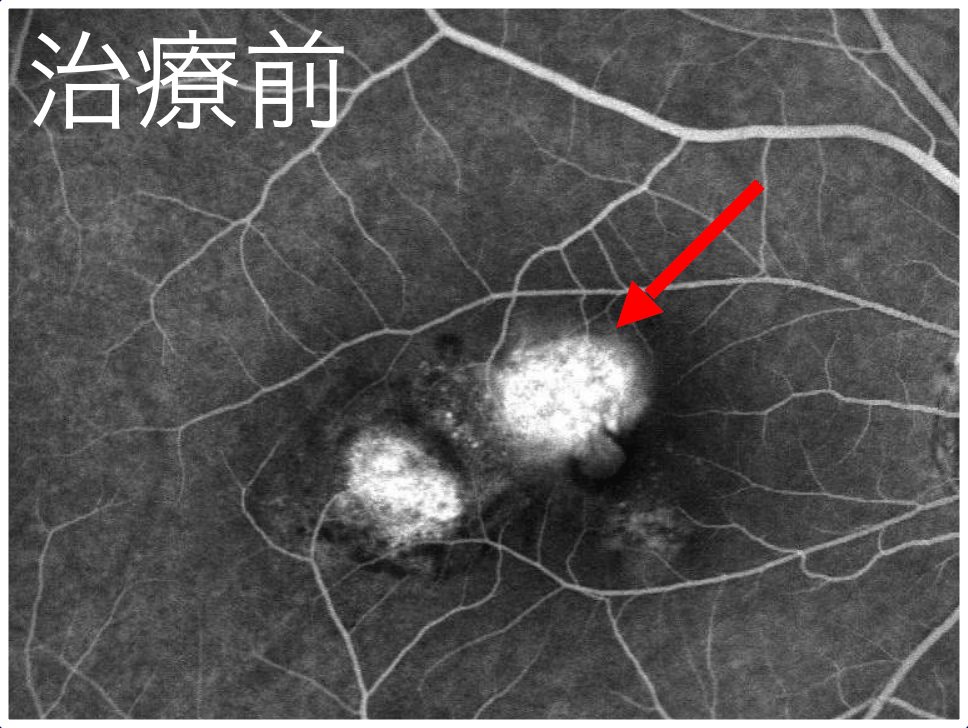
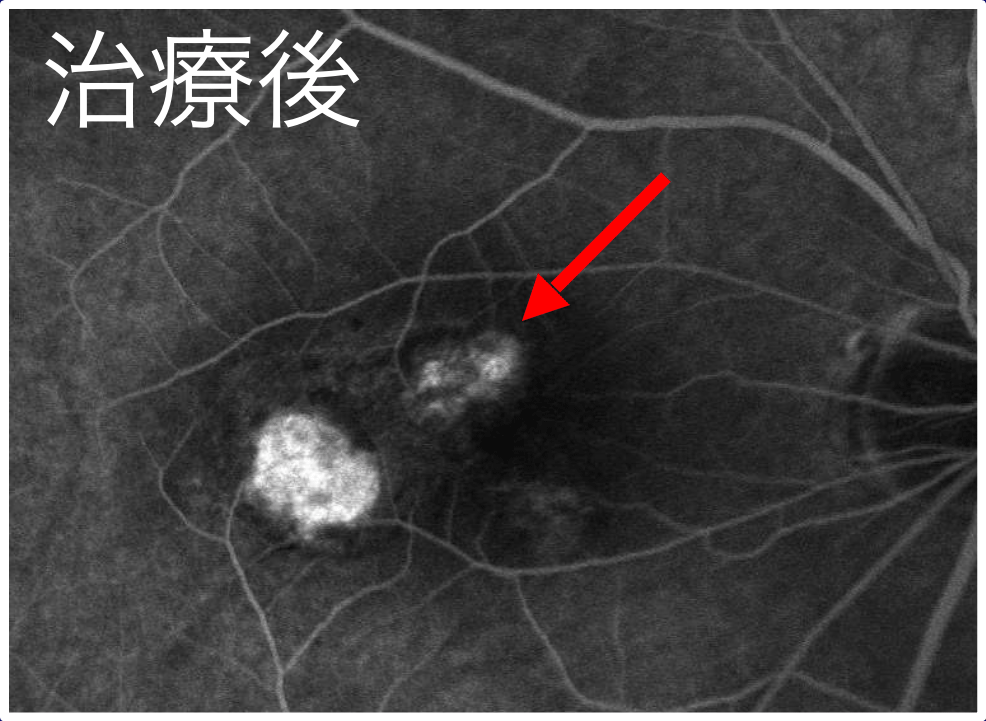
-
インドシアニングリーン蛍光眼底造影
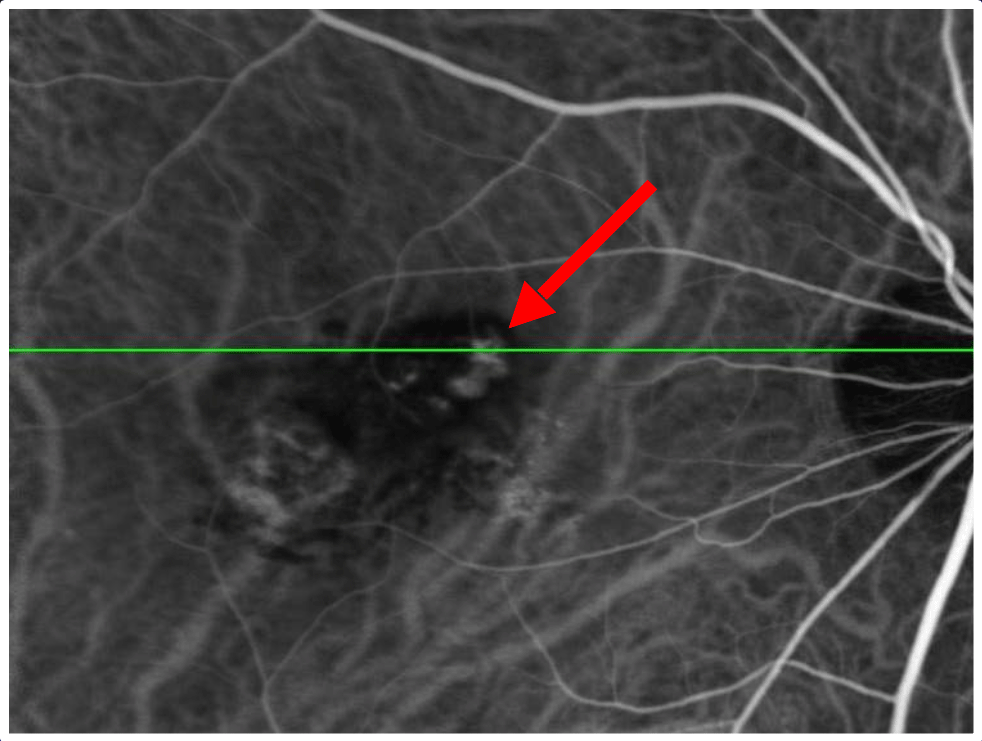
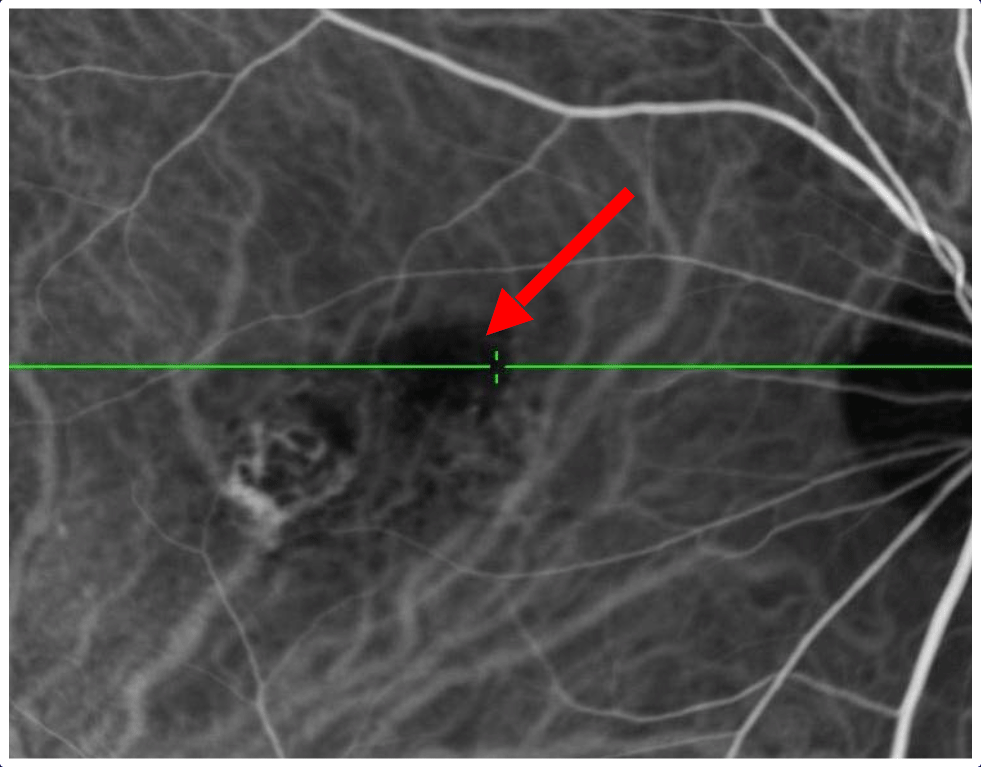
-
加齢黄斑変性症の予防
- 早期発見
アムスラーチャートで日頃から自分でチェックする。 - 早期治療
特に生活習慣病の方は日頃から眼の症状に注意し、加齢黄斑変性症が疑われる場合は、眼科専門医に早めに相談する。 - 加齢黄斑変性症の予防①
禁煙は非常に大切です。滲出型加齢黄斑変性症の症状発生の予防のために、サプリメントを服用する場合があります。 - 加齢黄斑変性症の予防②
食事、運動、ストレスなど、生活習慣に気を配る(亜鉛や抗酸化ビタミンが多く含まれている食品をとるように心がける)サングラスをかける
加齢黄斑変性症の治療
- 抗血管新生薬療法:新生血管の成長を活性化させる物質の働きを薬で抑える
- 光線力学的療法(PDT):新生血管を退縮させる
- レーザー:新生血管を焼く、もしくは温める
- 手術:新生血管を取り除く
治療①
「ルセンティス」という薬を眼に注射する、最新の治療法。新生血管の成長を活性化する物質として身体の中にある、VEGF(血管内皮増殖因子)の働きを抑える。視力が改善する。
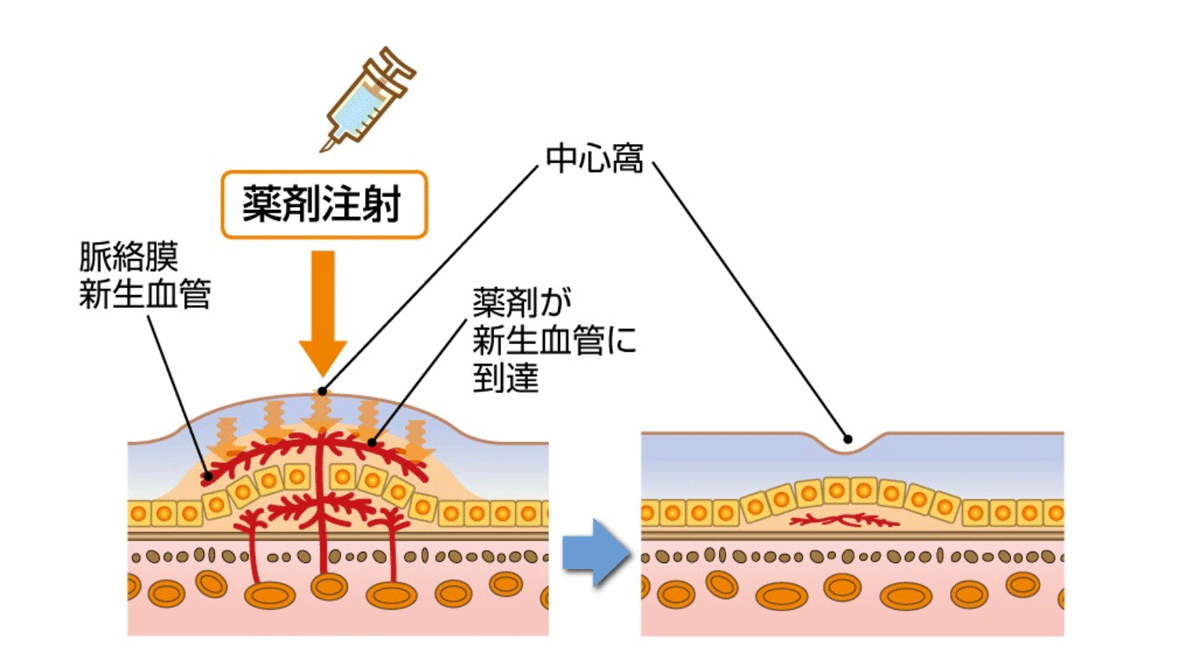
EGF(血管内皮増殖因子)とは:脈絡膜の血管内皮細胞を活性化させ、新生血管の成長を活性化させる物質です。
治療②
「ビスダイン」という光に反応する薬剤を静脈に注射した後、弱いレーザーを照射することでビスダインを活性化し、新生血管を退縮させる。正常な網膜を傷つけない。視力の低下が抑えられる。
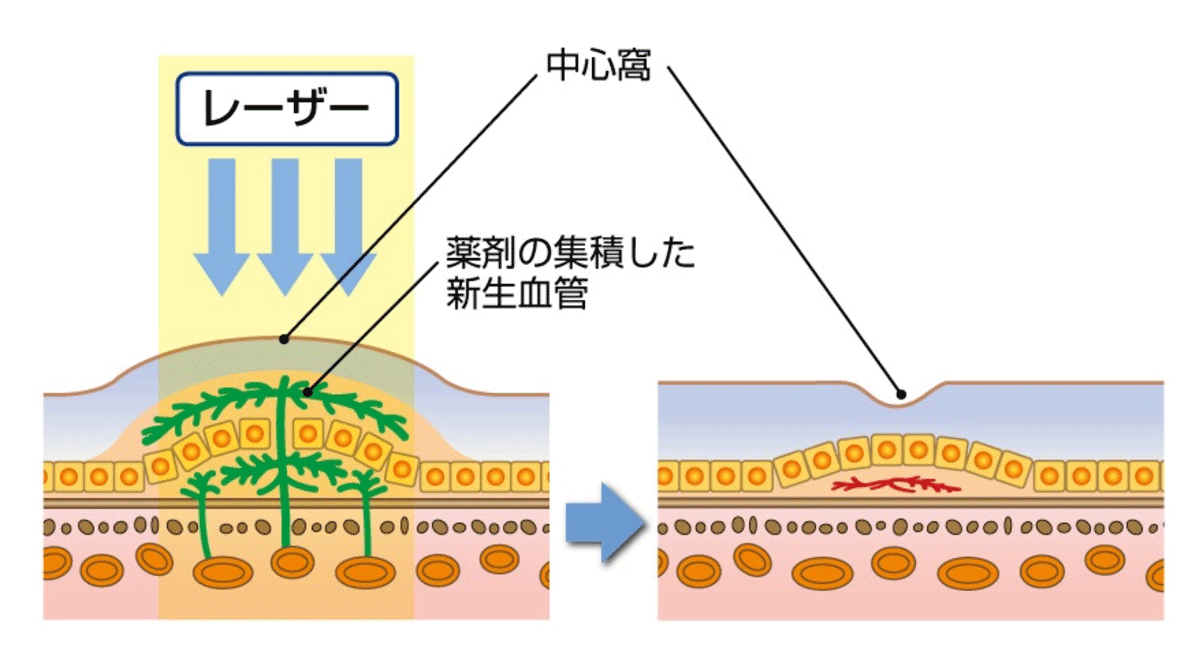
治療③
-
レーザー光凝固
新生血管が中心窩にない場合の治療法。レーザー光で新生血管を焼き固めるため、レーザー照射した場所の視力が欠ける。周囲の正常組織にダメージを与える問題がある。
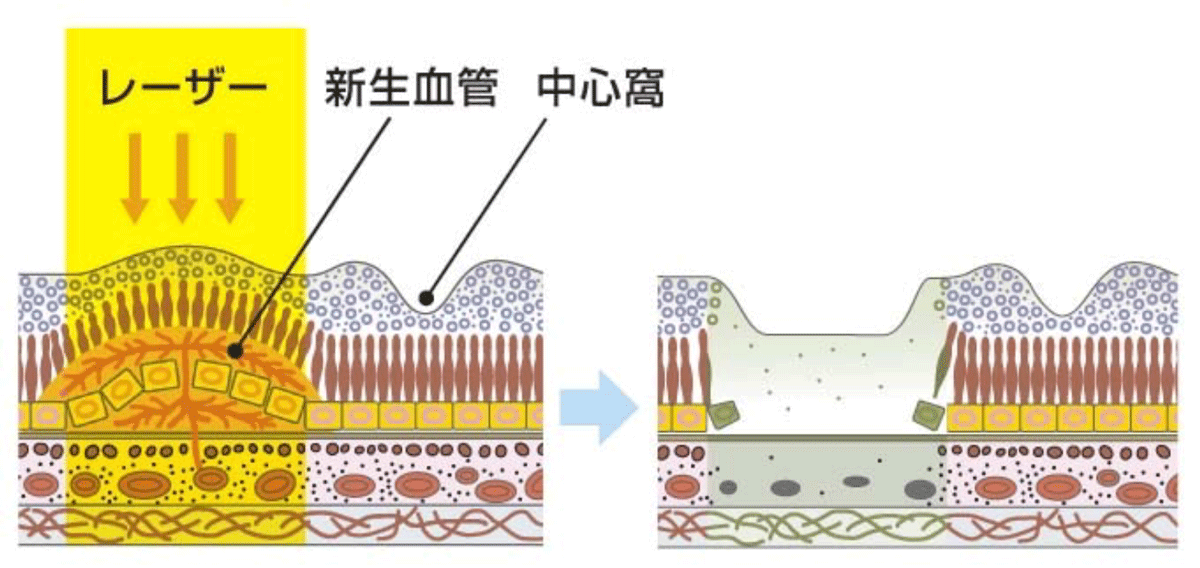
-
経瞳孔温熱療法(TTT)
弱いレーザーを新生血管に照射し、軽度の温度上昇により新生血管の活動性を低下させる。
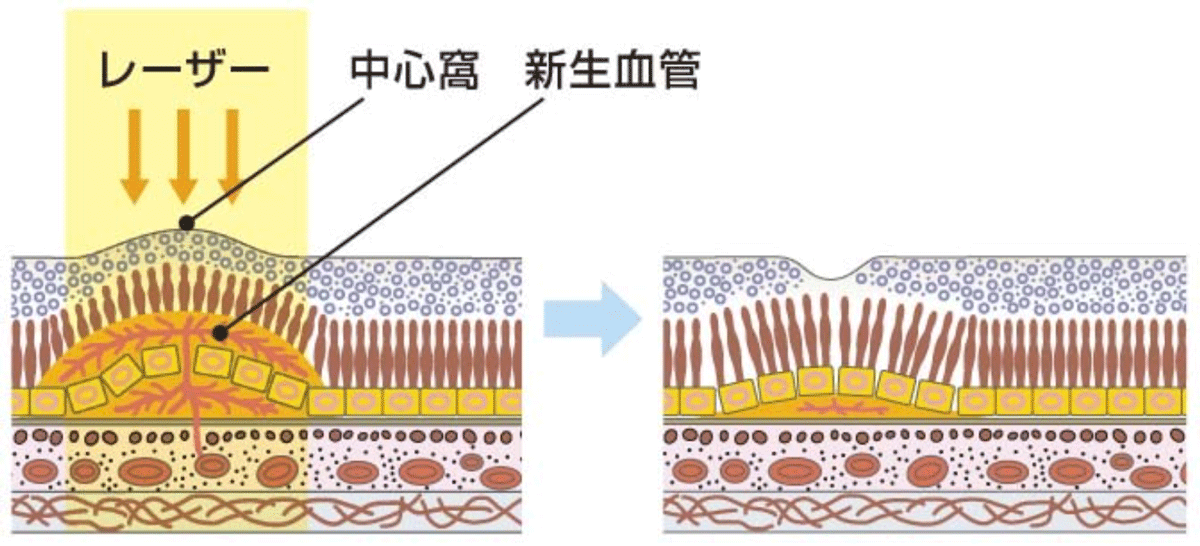
治療④
-
新生血管抜去術
新生血管を取り去る。新生血管が中心窩にある場合にも実施されるが、中心窩を傷つける危険性もある。
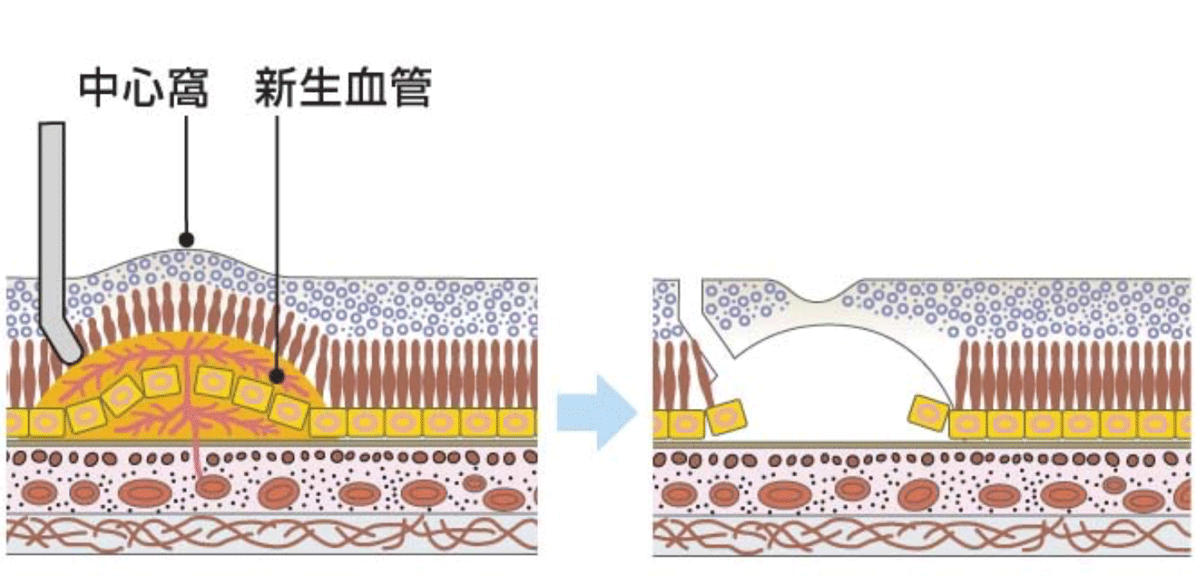
-
黄斑移動術
中心窩の網膜を新生血管から離れた場所に移動し、中心窩の働きを改善する。複視(ものが二つに見える)などの副作用がある。
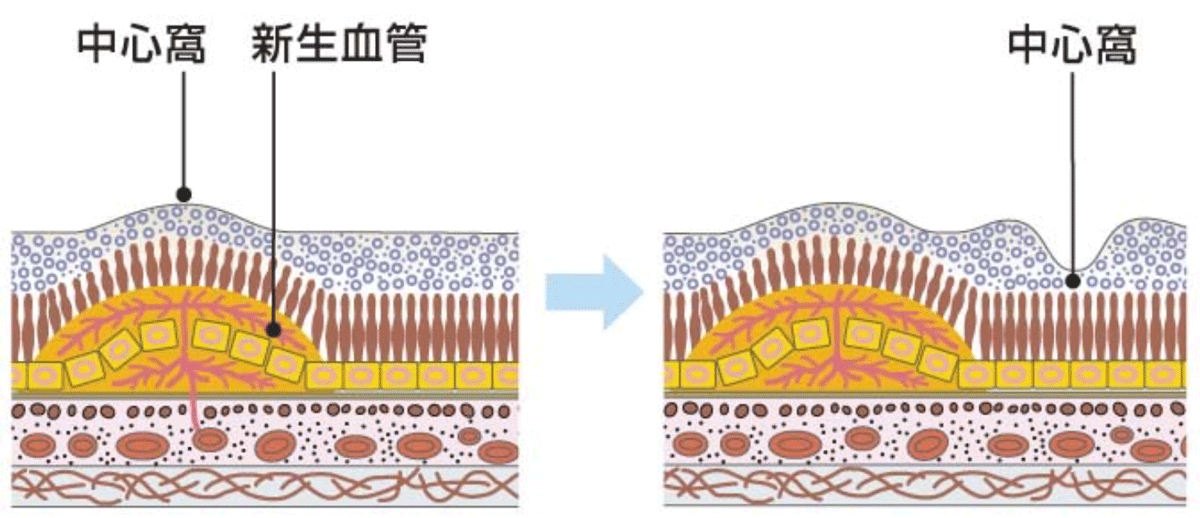
加齢黄斑変性症は次の点に注意
加齢黄斑変性症の症状を老化現象と考えてしまう人が多い。両眼とも発症する割合が高い。現在行われている治療は、継続的な治療が必要である。
ルセンティス治療について
滲出型加齢黄斑変性症の原因である、新生血管の増殖や成長を直接抑える。1ヵ月に1回、眼に注射をすることを3ヵ月間繰り返す(導入期)。その後、診察検査で症状をみながら、必要に応じて注射をする(維持期)。視力が改善する。
ルセンティスの視力改善効果
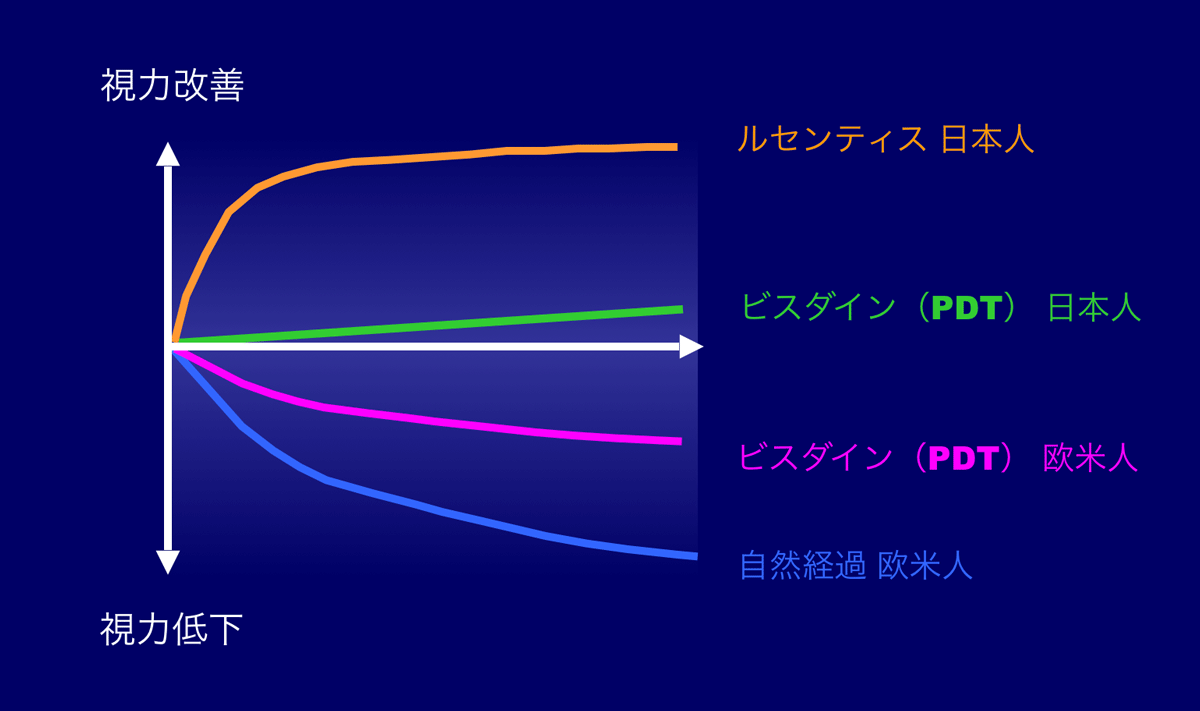
日本人のルセンティスの視力改善効果
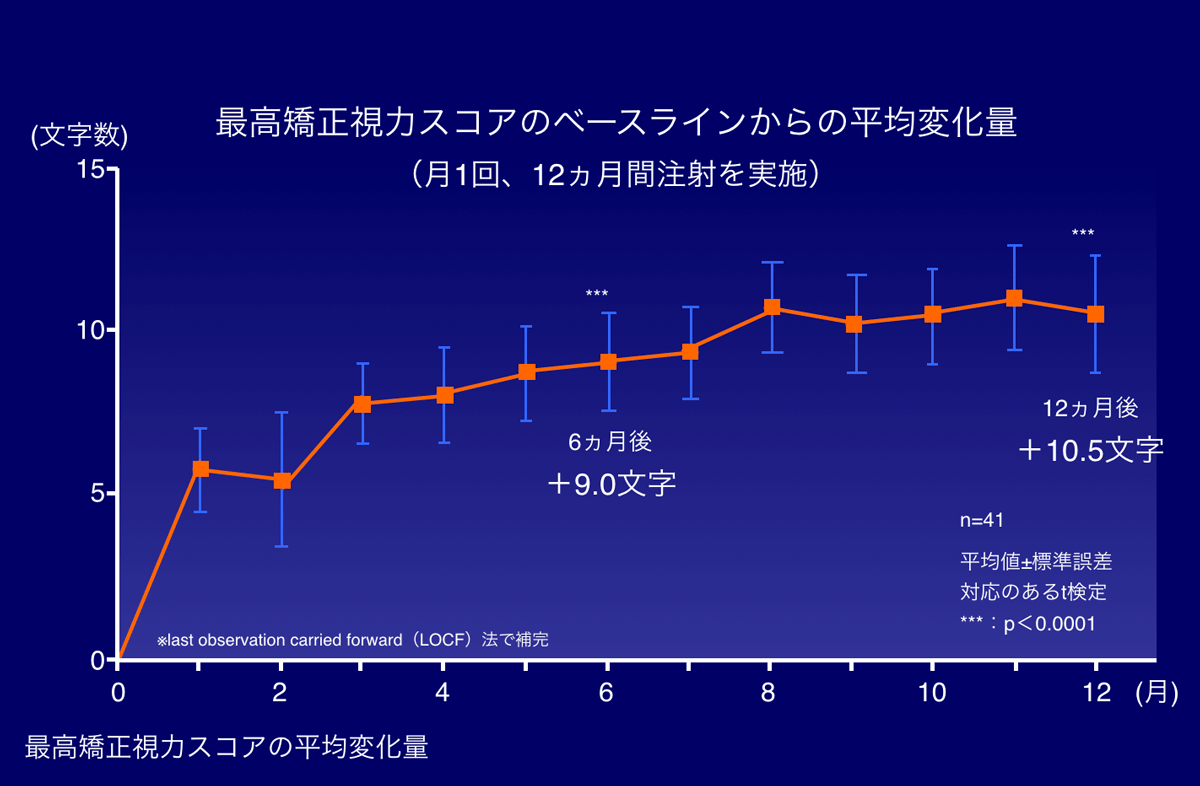
ルセンティス治療のスケジュール
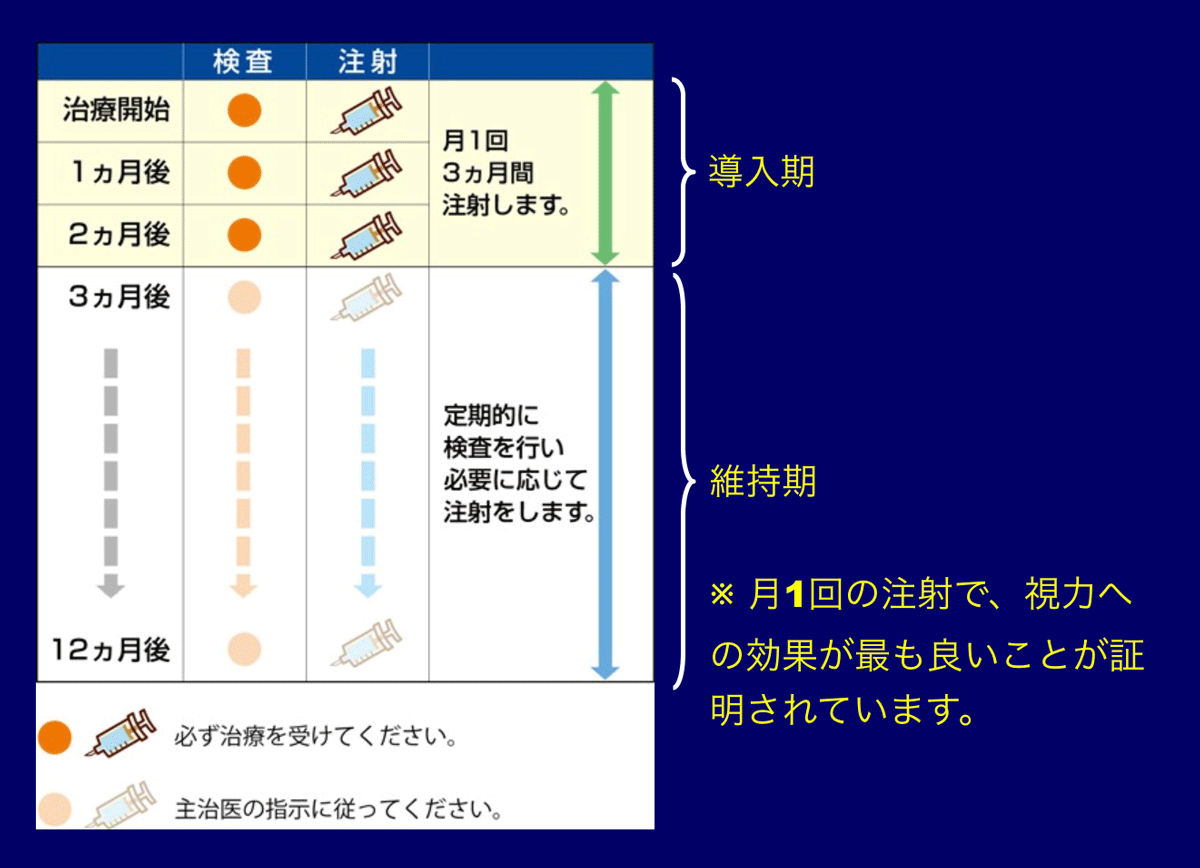
ルセンティス治療の手順
-
原則として、ルセンティス治療を受ける前3日間と受けた後3日間は、注射部位の感染を予防するため、抗菌点眼剤(抗生物質の目薬)を点眼する。
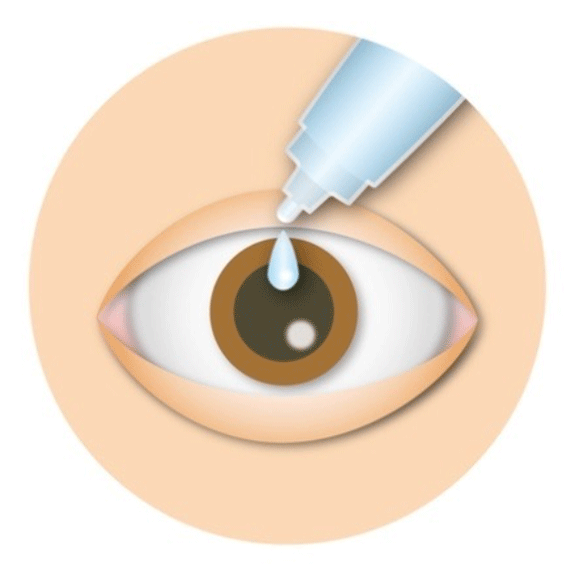
-
治療日には、担当医が眼の消毒と麻酔をし、麻酔薬を点眼や注射等した後で、ルセンティスを注射する。
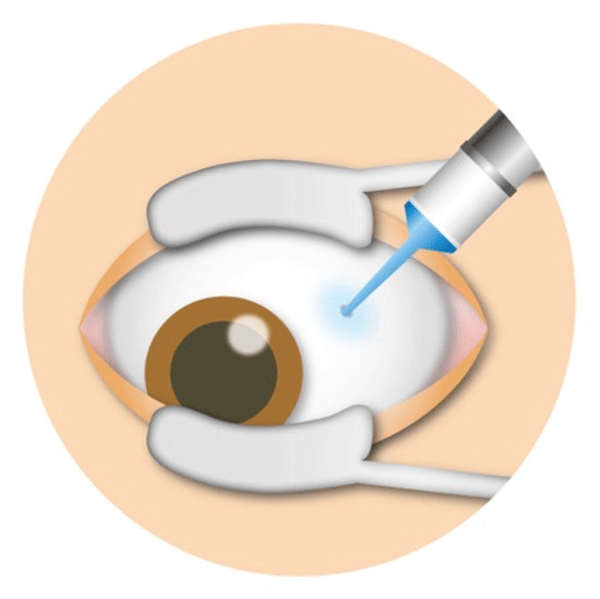
ルセンティス注射後の注意
注射後1週間程度は、感染のおそれがあるため以下の症状に注意し、あらわれた場合は主治医に連絡をします。
- 眼の痛みや不快感
- 眼充血の悪化
- 目やに
- 光に対する過敏症
- 飛蚊症(目の前を小さな浮遊物が飛んでいるように見える)
- 視力の低下を感じる
ルセンティス治療の副作用
外国人の患者さんで、脳卒中の報告があります。重大な副作用として、注射後の眼の炎症(眼内炎)があります。
- 眼圧の上昇
- 視力の低下
- 眼痛
- 網膜出血 など
治療について
内服薬で効果があるものはないのですが、抗酸化ビタミンと呼ばれるビタミンC、Eのほかに亜鉛などを加えたサプリメントは初期の徴候が出ている方の進行予防に効果があることがわかっているため、当院でも取り扱っております。喫煙は悪化の原因となりますので喫煙者の方は止めるべきです。その他に硝子体注射や光線力学療法といった治療が行われていますが、当院では入院の必要がない硝子体注射のみ行っています。硝子体注射は眼の中に直接、効果のある薬剤を入れる方法です。一度で済むことはほとんどなく、検査で網膜の状態を確認しながら1ヶ月以上間隔をあけて注射を追加していきます。